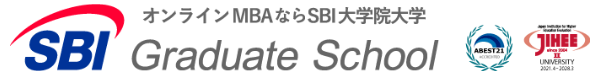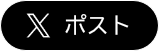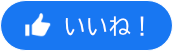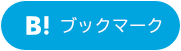本学教員がゼロから立ち上げを支援したビジネス
案内メール

本学教員の多くは実務家です。
MBAコースで教鞭をとるだけでなく、ビジネスの現場でも活躍しています。
しかしどんな事業で、どのくらいの成果を上げているのかはわかりにくいのが現状です。
そこで今回は本学教員のビジネスにおける成果として、
大月延亮先生の事例をご紹介します。
大月先生は本学の科目「事業計画演習」を担当している講師です。
一方で、株式会社カタリストの代表取締役社長という顔も持っています。
ご紹介するのは、自由貿易協定(FTA)活用に必要な原産性調査のデジタル化に関する事例です。
今年6月19日の日本経済新聞に取り上げられました。
外部記事:トヨタなど車9社、FTA申請で連携 新システムで時間短縮
ごく最近の成果としてご覧ください。
■自由貿易協定(FTA)とは
説明の都合上、まずは自由貿易協定(FTA)を簡単に解説します。
FTAとは、特定の国や地域間で物品の関税やサービス貿易の障壁等を
削減・撤廃することを目的とする協定です。
FTAを結ぶと低い関税率が適用されるため、FTA相手国と取引のある企業にとっては
大幅なコスト削減や相手国市場での価格競争力向上に繋がります。
製品や食品が安く手に入るので消費者にも利益があります。
■FTAを利用したい企業の悩み
企業にも消費者にもメリットの大きいFTAですが
「協定の適用を受けるために物品毎に原産性を証明する書類を作るのがとても大変」
という問題がありました。
取引先間をまたがる書類作成のための調査に11か月ほどかかることもあり、
FTAを利用したい企業にとってはこれが悩みの種だったのです。
■共通システムで書類作成業務を大幅に効率化
この悩みを解決するために開発されたのが、原産性調査プロセスを標準化し、
取引先間の情報のやり取りを円滑化する統一システムです。
クラウド上に構築されたデジタルワークフローを通じて、効率的に書類作成を行うことが可能になります。
このシステムにより手続きにかかる時間が7か月程度に短縮されるため、
よりスピーディーに関税削減メリットが得られるほか、
同じシステムを複数の会社で利用できるためシステムの投資コストも抑えることができます。
つまり国際競争力のアップに大きく貢献するシステムなのです。
サービス開始と同時にトヨタ自動車やホンダ、デンソーなど9社がこれを利用し、
自動車業界、自動車部品業界が連携してFTA活用の効率化を進めることになっています。
世界的に見ても、企業の枠を超えてFTAの手続きを共通化する例はめずらしく、
非常に先進的な事例となりました。
■ゼロから関わり、運用支援まで
大月先生が代表を務める株式会社カタリストは、コンサルタントとしてこの仕組みの構想策定から関わり、
システム開発、サービス運用までを支援しています。
サービスのリリース元は別の会社なので、表からは見えないところでの活躍ではあります。
しかしリリースと同時に自動車メーカー9社に利用されるサービスをゼロベースで立ち上げたわけですから、
これは大きな成果と言ってよいでしょう。
また構想策定から約2年半でリリースにこぎつけたスピード感も特筆すべきものでした。
■まとめ
今回は本学教員のビジネスにおける最近の成果をご紹介しました。
ざっと内容はおわかりいただけたかと思いますが
ゼロからどうやってこのビジネスを作り上げたか想像がついたでしょうか。
「やった人でないとわからない経験知」を持っているのが、実務家教員の強みです。
「この先生はどんなビジネスを手掛けてきたんだろう」
という視点で教員を見ると、また違った角度でMBAスクール選びの材料が見つかるでしょう。
(この記事は2020年7月17日配信の案内メールを一部改変したものです)