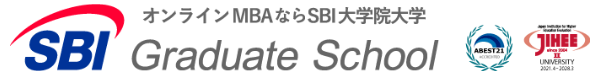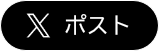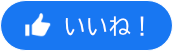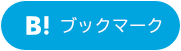学長北尾吉孝がコロナ禍の今考えていること
メルマガ

デジタルシフトタイムズにて
本学学長 北尾吉孝と客員教授 田中道昭の対談が公開されました。
>>菅政権で加速する金融大再編。金融×デジタルシフトの第一人者、SBI北尾社長の見据える未来を田中道昭教授が読み解く
この対談は「SBI大学院大学特別講義」という位置づけでもあり、
北尾がSBI大学院大学をどのように考え、現在の時流をどうとらえているかがわかる
内容となっています。
本学は他校と比べて特殊な考え方に基づいて作られた学校です。
今回はこちらの対談からの抜粋をもとに、学長の北尾が現在考えていることをお伝えしていきます。
■哲学・こだわり
2008年の建学時、北尾は起業を目指す人を対象にした学校にしたいと考えていました。
経営者はたくさんの人に影響を与える存在だからです。
経営者というのは影響力がかなり大きい存在です。そこに働く従業員、取引先、そしてお客様に対し、自分の志を広く世に伝播させ、世の中のためになることをしていく。併せて、人の指導者になるということですよね、起業家になるということは。
では、経営者にとってもっとも重要な要素は何か。
北尾のたどり着いた答えは「人間力」でした。
私は究極、人を動かすのは何かというと、人間力ではないかと思うのです。ですから、そういう人間力を醸成するような教育観は世界広しといえどもなかなかないなと思いました。
■門戸は広く
本学が開校した2008年は、今と比べるとネット環境はまだまだ未発達な状態でした。
そんな中で大学院ではなく「大学院大学」、しかもオンラインで学べるようにしたのは、
一定の学力や見識があって働いている人に広く門戸を開けるためです。
大学を卒業した人のための大学院という形に位置付けず、大学院大学という非常に珍しい形態で作りました。高卒の人でも、ここを卒業できたら文科省認可のMBAが取れて、大学院を卒業したという立場になれるようにしたいと。そんな様々な思いの中で作ったのです。そして、働く人を対象にしていますから、オンラインでないと無理だと思いました。
■コロナ禍のとらえ方
「天の時」「地の利」という見方でコロナ禍をとらえると、プラスの面が見えてきます。
まずは「天の時」の視点。
インターネットの世界でいままでやってきたことが、コロナ禍によって追い風を受けました。
大変な状況になっている業界は沢山ありますが、我々はDay1からインターネットの世界に入り込んで今日までやってきた。ますますデジタルトランスフォーメーションが進むと、我々がますます強くなっていく。今はそういう状況で、全ビジネスが非常に好調に推移しています。ですから、「天の時」を、そういう意味では得られているということでしょう。
「地の利」としては、「事業ポートフォリオの拡大」を挙げています。
これまで培ってきたITの強さが例えば医療情報の整理をする事業に
つながったりするのです。
医療情報というのは、もっと分析的に、疫学的に統計化していくような、そういう世界が必要です。そういう意味では、この今の状況下で、そこにいろんなITのテクノロジーを加味して、新しい事業体を作っていく。そういう事業ポートフォリオの拡大を今、しつつあります。
■デジタル化が進む今、大切なこと
北尾はインターネットの世界が広がっていく中で大切なことが2つあると言います。
一つは「人を欺かないこと」。
多くの人は、インターネット上の情報に一種の信頼感をおいて、「このお弁当は美味しそうだ」と注文するわけですよね。このインターネットの世界で、インターネット以前の世界に比べて大事な要素というのは、やはり人を欺かないこと。要するに信ですね。これが非常に大切。
もう一つは「思いやり」です。
インターネットの世界ほど、相手のことを思いやりながら、お客さんはどういったことに喜ぶのか。いろんな情報を集めながらそういうものを感知して、お客様の満足度を最大限に高めようとしていかないといけない。
■まとめ
以上、デジタルシフトタイムズの対談から本学学長 北尾吉孝の現在の考え方を
抜粋してお届けしました。
対談全体は前後編の記事にまとめられているほか、それぞれ22分と42分の動画として視聴することもできます。
今回ご紹介したのはほんの一部の内容ですので、他の内容もご覧になりたい方は下のリンクからぜひどうぞ。
>>デジタルシフトタイムズ